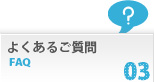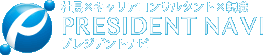305. 人がやらないことを
ノーベル賞 生理学賞の受賞を決めた大隅良典(おおすみ・よしのり)さん・東京工業大栄誉教授
「オートファジー」でノーベル賞を受賞!!
今回のノーベル賞受賞者である大隅教授が酵母を用いて、酵母を飢餓状態に置くと液胞と呼ばれる酵母が持つ小器官に多くの小さな粒状の物質が蓄積されていくのを顕微鏡で確認します。
オートファジーは酵母だけでなく人間にも共通してあるもので、この働きはがん細胞が増殖していく過程やアルツハイマー病などにおける異常なたんぱく質の集積にも関連していることを解明しました。
これらの病気の病態の解明や治療薬の開発にも、非常に重要な役割を果たすものと考えられます。
会見で大隅さんは、今回の受賞につながった研究を始めたいきさつについて、
「人がやらないことをやろうという思いから、研究を始めました。
強調したいのは、この研究を始めたときに必ず『がん』の研究につながるとか、
『寿命』の研究につながると確信して始めたわけではありません。
そういうふうに、基礎研究が転換していくんだということを強調しておきたいです」と述べ、
自然科学の分野での基礎研究の重要性を強調しました。
また、「サイエンスは、どこに向かっているのかがわからないところが楽しいのです。
『これをやったらよい成果につながります』と言うのは、サイエンスにとってはとても難しいことです。
すべての人が成功するわけではありませんが、チャレンジすることが科学の精神であり、
その基礎科学を見守ってくれる社会になってくれることを期待したいです」と述べました。
今、ノーベル賞学者がたくさん出てるから日本はすごいんだというのはとっても間違っていて。
日本の科学は空洞化するよという危機感を非常に強く持っています。
そういうことがずっと続く、次から次へとそういう若い人が生まれてくる体制を作ってくれないと。
あと何年か現役でいる間は、かなりの自分の力をさいてみようと思っています。
若い人が少しロングタームでですね、2年間で何するというのではなく、
まずは大きな問題設定ができて、こんなことにチャレンジしたいということが5年10年ぐらい先まで若者が考えて
もちろん日々は具体的なことというのに左右されますけど。
こういう問題を解きたいんだと若い人たちが本当に思えて、
そういうことをサポートするような社会の雰囲気というのがとっても大事なんだと思っています。
科学はいま役に立つことがとっても問われていますが、役に立つというのは非情なもので。
役に立つというのが、来年、薬になったということだと、13年後に薬になったというとらえ方されると、本当にベーシックなサイエンスは死んでしまうと思うので。
私たちがどんなことを理解していったらいいかっていうふうに思うかということをとても大事にする社会。
科学を人間の文化だと思って、社会が支えてくれるような、
研究者も私たちはそういうのに支えられていると自覚するような時代に来ているのではないかと私自身は思っています。
若い世代へのメッセージを求められた大隅さんは
「今、なかなか子どもたちが自分の興味を表現することが難しい時代になっている」
と述べたうえで、「『あれっ』と思うことがたくさん世の中にあるので、
子どもたちには、そうしたことへの気付きを大切にしてほしいです。
分かっている気分になっているが、何も分かっていないことが、生命現象にはたくさんあります。
子どもたちには『なんとかなるさ』というくらいの気持ちで、チャレンジしてくれる人が増えることを強く望んでいます。
それと同時に、そうした子どもたちを支える社会であってほしいです」と述べました。
最後に大隅さんは、ノーベル賞の賞金の使い方について
「この年になって豪邸に住みたいわけでもありません。
若い人たちの研究をサポートができるようなシステムができればいいと思います。
私が生きている間に、一歩が踏み出せればいいなと思っています」と述べました。
以上抜粋
2016/10/20(木)
株式会社グローバルサポート
本社営業所:兵庫県芦屋市業平町4-1イム・エメロード5F
JR芦屋駅 徒歩3分 梅田より15分 三宮からも10分です。
岡山営業所:岡山県倉敷市阿知1-7-2くらしきシティプラザ西ビル8階
フリーダイヤル:0120-80-9686
メールアドレス:info@president-navi.com
転職相談は、全て無料です。
まずはお気軽にご登録下さい♪

あなた様からのご応募を、心よりお待ちしております。