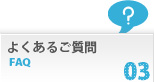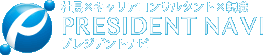今年2月、財務省は国民負担率が2023年度には46.8%になる見通しだと発表しました。
社会保障に詳しい関東学院大学経済学部の島澤諭教授によると、「“国民負担率”は、租税負担および社会保障負担を合わせた公的負担の、国民所得に占める割合です。租税負担とは、所得税や法人税、ガソリン税、消費税など、ありとあらゆる税金のこと。社会保障負担は健康保険料や厚生年金保険料などです。国民負担率が高ければ高いほど、年収に対して公的負担が大きいということになります。岸田内閣では“異次元の少子化対策”を打ち出しています。国民所得を財務省試算のとおり421.4兆円、少子化対策の費用を3.5兆円とすると、国民負担率は0.8%押し上げられます。つまり先日発表された財務省の見通しよりさらに高く47.6%に達する可能性も。近年中に50%を超えるのも、ほぼ間違いないでしょう」との事。
国民負担率が上がることで、どれほどわれわれの家計に影響があるのでしょうか?
酒居会計事務所の酒居徹地さんが、年収500万円の40代会社員と、配偶者(収入なし)、高校生の子供がいる場合の手取り額の推移を試算していたので紹介したいと思います。
まずは国民負担率がまだ35.6%だった2000年は、健康保険料が16万7760円、厚生年金保険料が31万8900円、雇用保険料が2万円、所得税が9万4600円、住民税が6万8100円だったため、年収500万円家庭の手取り額は、433万640円でした。
ところが国民負担率が37.2%に上がった2010年には、健康保険料が26万6千172円、厚生年金保険料が39万5千27円、雇用保険料が3万円、所得税が6万8千900円、住民税が15万5千700円となり、手取り額は408万4千201円となり、20年あまりで約33万円も手取りが少なくなっています。
しかもこの期間には消費税の増税なども施行されたため、消費額も増えています。
物価高騰に加え介護保険料なども値上げが続いている昨今、国民の負担が増えれば増えるほど将来への不安から少子化は加速します。
政府には何とかしてこの悪循環から抜け出す打開策を打ち出してもらいたいものです。
株式会社グローバルサポート
本社営業所:兵庫県芦屋市業平町4-1イム・エメロード5F
JR芦屋駅 徒歩3分 梅田より15分 三宮からも10分です。
岡山営業所:岡山県倉敷市阿知1-7-2くらしきシティプラザ西ビル8階
フリーダイヤル:0120-80-9686
メールアドレス:info@president-navi.com
転職相談は、全て無料です。
まずはお気軽にご登録下さい♪

あなた様からのご応募を、心よりお待ちしております。